
天日塩で炒めた塩作り
天日塩はもともと水分が多いので白菜や漬物用や醤油、味噌などに使いますが、水分を飛ばして炒めて使うと味を調える料理用としてもとても良いそうです。 人工添加物がない天然材料なのでさらに良いです。 塩の場合は人工添加物がたくさん入っているんですよ。 天日塩にはカルシウム、マグネシウム、亜鉛、カリウム、鉄などの無機質が多く、体にも良いそうです。 それでは天日塩で炒めた塩を作ってみます。~~
6 人分
999 分以内

밥심은국력
- 材料
-
-
天日塩5柄杓
-
お湯少し
-
- 調理順
-
STEP 1/10天日塩は塩水を抜くと苦味がなくなるのでおいしいですが。 塩水を抜く最も簡単な方法は、高さのある密閉容器を利用して、底に新聞紙を厚く敷きます。 その上に天日塩を袋ごと入れておくと、看守が抜けるそうです。 こうして3年経った天日塩です。 新聞紙は、最初は看守が流れるにつれて濡れ始めるので、たまに取り替えなければなりません。
 STEP 2/10塩水抜きの天日塩で料理用の塩を作ってみようと思うのですが、ふるいに塩を入れ、冷水で素早くすすぎます。 お湯は塩が溶けるので絶対にだめです。 塩をすすいだ冷水を見ると、底に塩があまりないのがわかりますよね? 素早く洗うと絶対に塩が溶けず、すすいでくれる理由は天日塩にあった不純物を取り除くことができるからです。 ふるいにかけて水気を切るのですが、2~3時間ほど放置しておきました。
STEP 2/10塩水抜きの天日塩で料理用の塩を作ってみようと思うのですが、ふるいに塩を入れ、冷水で素早くすすぎます。 お湯は塩が溶けるので絶対にだめです。 塩をすすいだ冷水を見ると、底に塩があまりないのがわかりますよね? 素早く洗うと絶対に塩が溶けず、すすいでくれる理由は天日塩にあった不純物を取り除くことができるからです。 ふるいにかけて水気を切るのですが、2~3時間ほど放置しておきました。 STEP 3/10ステンパンを使って塩を炒めてくれるのですが、その理由はコーティングパンを使うと天日塩の太さと硬さのためコーティングパンに傷がつくからです。 コーティングパンはコーティングが剥がれると発がん物質が出る可能性があります。 ステンパンを使用するときは、常に予熱します。 火を弱め、水気を切った天日塩を炒めます。 最初の塩の色は少し噛むので、色が薄くなっていましたが、水分が飛んでいくにつれてだんだん白くなります。 それからもっと長く炒めてみると、また色がこんがりしてきます。 塩の量によって炒める時間が少し違いますが、色が黄色くなるまで炒めるだけです。 普通15~20分ほどヘラでかき混ぜながら炒めます。
STEP 3/10ステンパンを使って塩を炒めてくれるのですが、その理由はコーティングパンを使うと天日塩の太さと硬さのためコーティングパンに傷がつくからです。 コーティングパンはコーティングが剥がれると発がん物質が出る可能性があります。 ステンパンを使用するときは、常に予熱します。 火を弱め、水気を切った天日塩を炒めます。 最初の塩の色は少し噛むので、色が薄くなっていましたが、水分が飛んでいくにつれてだんだん白くなります。 それからもっと長く炒めてみると、また色がこんがりしてきます。 塩の量によって炒める時間が少し違いますが、色が黄色くなるまで炒めるだけです。 普通15~20分ほどヘラでかき混ぜながら炒めます。 STEP 4/10スープやチゲにはこのまま使ってもいいのですが、ナムルやおかずのタレに入れる時は粒が太いので、この時はシュレッダーで挽いた方がいいそうです。
STEP 4/10スープやチゲにはこのまま使ってもいいのですが、ナムルやおかずのタレに入れる時は粒が太いので、この時はシュレッダーで挽いた方がいいそうです。 STEP 5/10炒めた天日塩は熱いので、お盆に広げて冷やします。
STEP 5/10炒めた天日塩は熱いので、お盆に広げて冷やします。 STEP 6/10シュレッダーに入れ、お好みの粒子サイズに挽きます。 私はきれいにすりおろしました。
STEP 6/10シュレッダーに入れ、お好みの粒子サイズに挽きます。 私はきれいにすりおろしました。 STEP 7/10残ったジュースの瓶を洗って干しておきました。 しかし、もし残っている水気がないかと思ってキッチンタオルを箸で押し込んでもう一度拭いてあげました。
STEP 7/10残ったジュースの瓶を洗って干しておきました。 しかし、もし残っている水気がないかと思ってキッチンタオルを箸で押し込んでもう一度拭いてあげました。 STEP 8/10粉砕した炒り塩です。 粒子がきれいでしょう?
STEP 8/10粉砕した炒り塩です。 粒子がきれいでしょう? STEP 9/10漏斗を使って瓶に入れます。
STEP 9/10漏斗を使って瓶に入れます。 STEP 10/10この病気で2本出ました。 見出紙を貼ってくれるといいですね。 天日塩でヘルシーな料理塩を作ってみてください。~~~
STEP 10/10この病気で2本出ました。 見出紙を貼ってくれるといいですね。 天日塩でヘルシーな料理塩を作ってみてください。~~~ 天日塩は海水を塩田に引き込み、風と日光で水分だけを蒸発させて作った塩です。 中国産天日塩との区分は、手で握った時によく砕けると国内産で(水分が多いため)、硬くて砕けないと中国産なんです。
天日塩は海水を塩田に引き込み、風と日光で水分だけを蒸発させて作った塩です。 中国産天日塩との区分は、手で握った時によく砕けると国内産で(水分が多いため)、硬くて砕けないと中国産なんです。
- トッポッキ おすすめレシピ
-
-
1
 TVレシピ通りに作ったスープトッポッキ4.79(43)
TVレシピ通りに作ったスープトッポッキ4.79(43) -
2
 [簡単な一人暮らし料理] 甘じょっぱい! 肉なしの宮中トッポッキ / 醤油トッポッキ作り4.83(47)
[簡単な一人暮らし料理] 甘じょっぱい! 肉なしの宮中トッポッキ / 醤油トッポッキ作り4.83(47) -
3
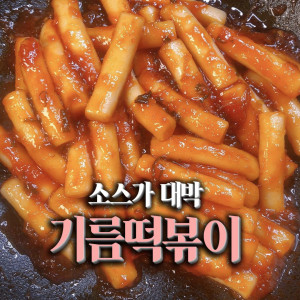 ソースがすごい油トッポッキ作り! *難易度簡単*ワンパンで終わり!4.84(51)
ソースがすごい油トッポッキ作り! *難易度簡単*ワンパンで終わり!4.84(51) -
4
 食べても食べてもまた食べたくなる即席トッポッキ4.75(53)
食べても食べてもまた食べたくなる即席トッポッキ4.75(53)
-
- チキン おすすめレシピ
-
-
1
 ジコバチキン100%真似する4.93(261)
ジコバチキン100%真似する4.93(261) -
2
 エアフライヤーで油一滴なしでサクサクチキン作り4.75(12)
エアフライヤーで油一滴なしでサクサクチキン作り4.75(12) -
3
 【超簡単】残ったチキンでおいしいおかず作り~5.00(11)
【超簡単】残ったチキンでおいしいおかず作り~5.00(11) -
4
 ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキンソース作り4.67(6)
ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキンソース作り4.67(6)
-